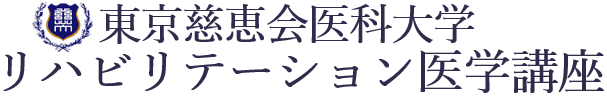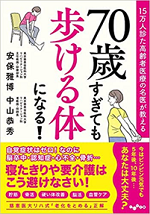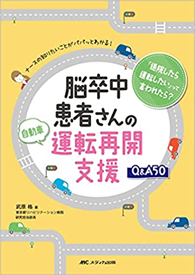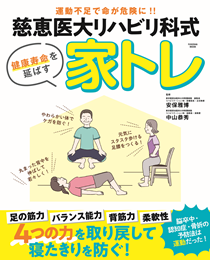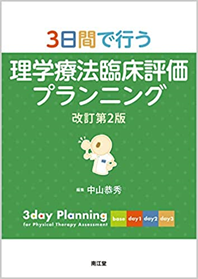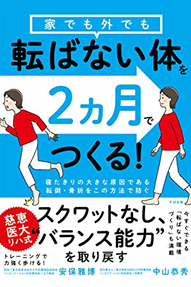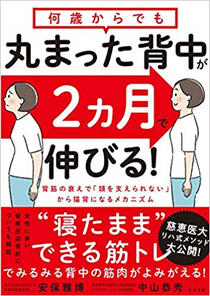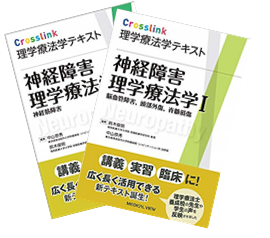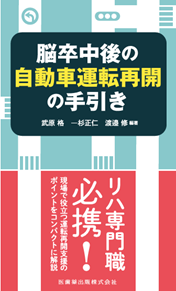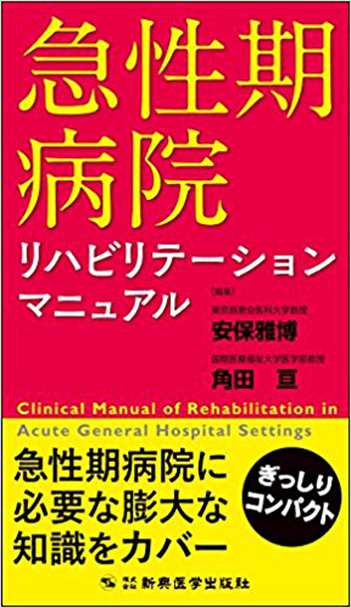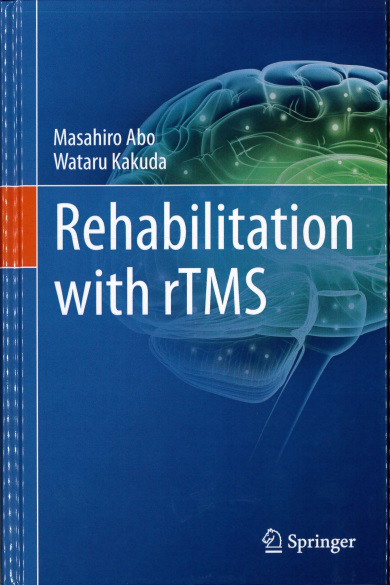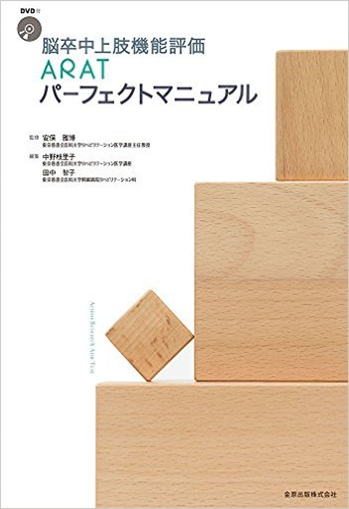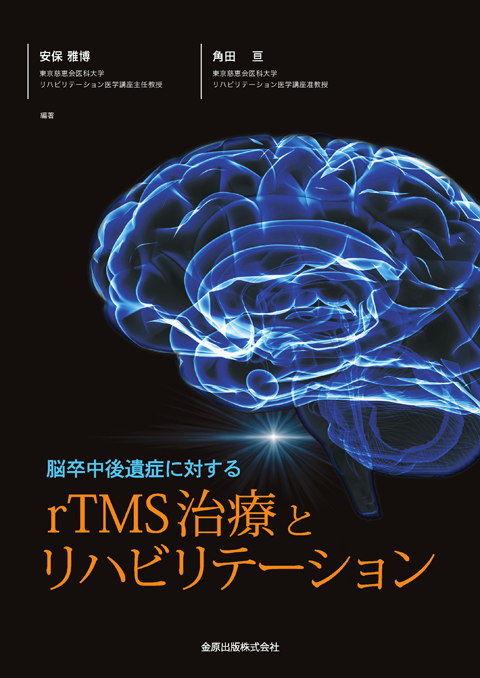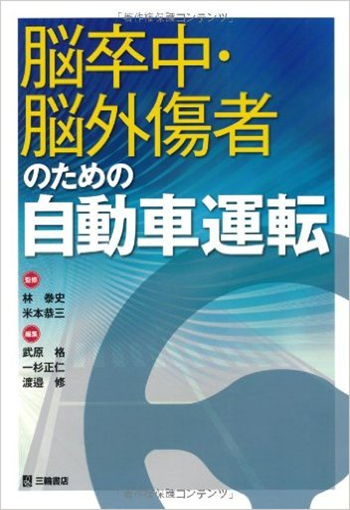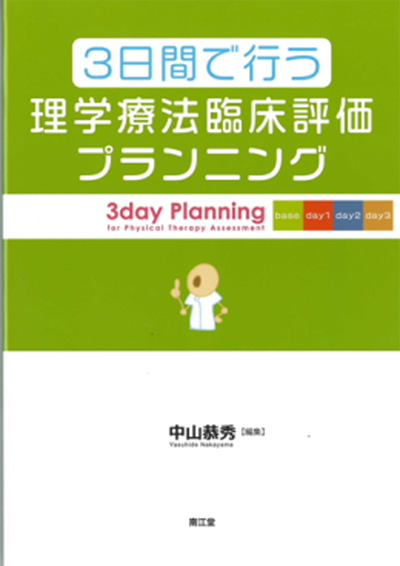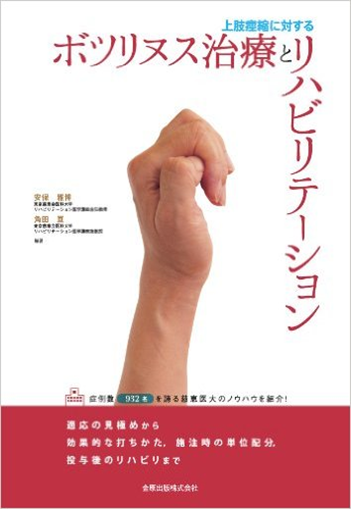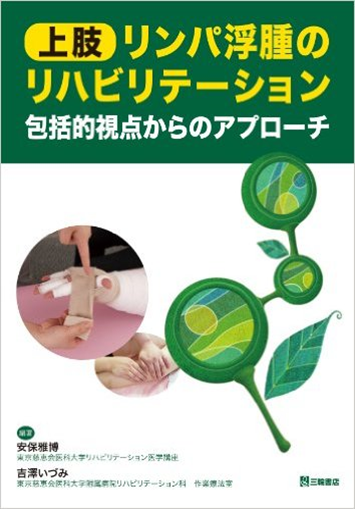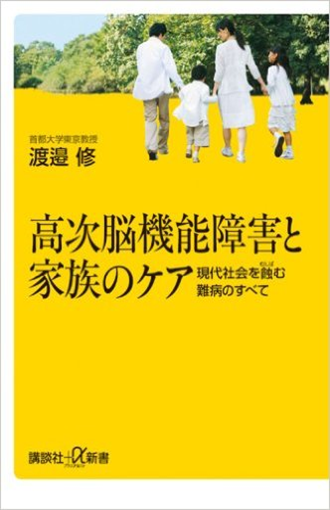書籍紹介

 |
上肢ボツリヌス療法とリハビリテーション医療 |
| 著者名:安保雅博(編集) | |
| 出版社:新興医学出版社 | |
| 発行年月:2020年8月 | |
|
ボツリヌス療法で極めて重要な要素となる的確な筋同定や正しい施注について、 本書では豊富な画像を用いながらより効果的な痙縮治療に結び付けられるかを解説している。 治療戦略、リハビリテーション指導、評価方法、EBMなど最新の知見と実践での経験も詰め込んだ充実の内容で構成! |
 |
書籍名:臨床医のための疾病と自動車運転 |
| 著者名:一杉正仁・武原 格(編集) | |
| 出版社:株式会社 三輪書店 | |
| 発行年月:2018年3月 | |
|
安全な自動車運転を行うために、脳卒中やてんかんをはじめ、様々な疾患の医学的な対応をまとめた本です。 運転の重要性に着目した臨床の最前線で活躍している医師達が執筆しており、日常診療の必携書と言えます。本書が直面する問題解決の一助となることを期待します。 |
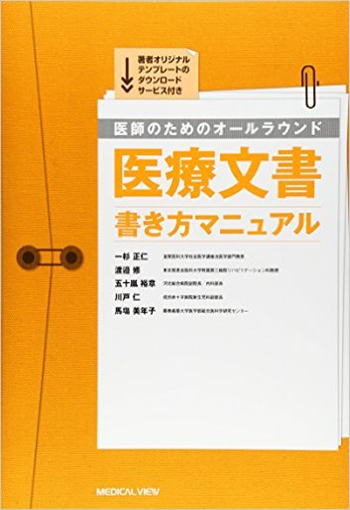 |
書籍名:医師のためのオールラウンド 医療文書の書き方マニュアル |
| 著者名:渡邉 修(共著) | |
| 出版社名:MEDICAL VIEW | |
| 発行年月:2015年07月 | |
| 日々の診療の中で医療書類を記載する方法を、正確かつ簡潔に記載しました。見開き2ページの中に具体的な記入例と注意点、書類の提出先やちょっとしたポイントが掲載されているので、この1冊で完璧な書類を作成することができます。 |
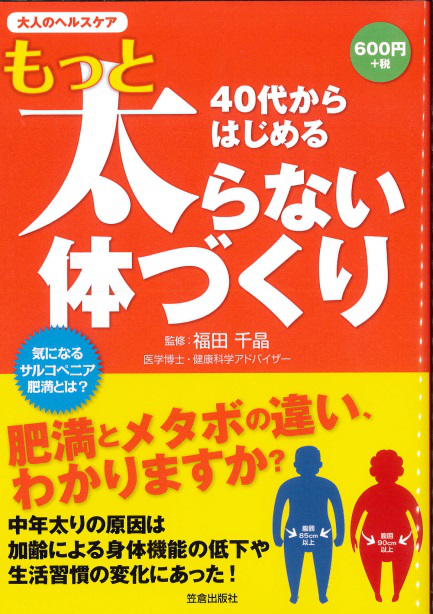 |
書籍名:40代からはじめるもっと太らない体づくり |
| 著者名:福田千晶(監修) | |
| 出版社:笠倉出版 | |
| 発行年月:2015年04月 | |
| 40歳を超えるころから右肩上がりの体重増加をしていました。この本のよいところは、keyになる文章にアンダーラインがあり、読みやすく理解しやすいです。そこだけ読んでも十分理解できます。個人差はありますが、ちょっと総カロリーに注意したら5kgほど痩せました。(文責:安保雅博) |
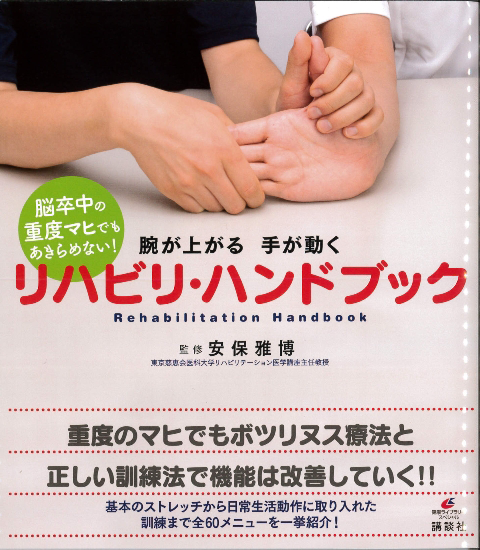 |
書籍名:脳卒中の重度マヒでもあきらめない!腕が上がる手が動く リハビリ・ハンドブック |
| 著者名:安保雅博/監修 | |
| 出版社:講談社 | |
| 発行年月:2014年11月 | |
|
脳卒中による上肢麻痺で、ほとんど手が動かない人のための訓練本です。重度の麻痺でもボツリヌス毒素と正しい訓練をすると機能が改善することがわかりました。 さあ、頑張って少しでもよくしましょう。(文責:安保雅博) |
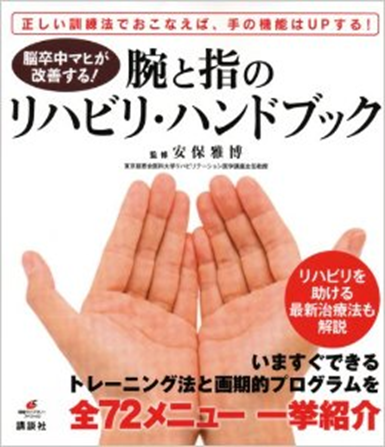 |
書籍名:脳卒中マヒが改善する!腕と指のリハビリ・ハンドブック |
| 著者名:安保雅博(監修) | |
| 出版社名:講談社 | |
| 発行年月:2011年09月 | |
| 脳卒中後遺症による上肢麻痺に対しての訓練本です。自力で少し肘が伸びる指が開く患者さん向けの本です。これにより基礎をしっかりさせ、反復性磁気刺激により、より改善効果を目指します。(文責 安保雅博) |
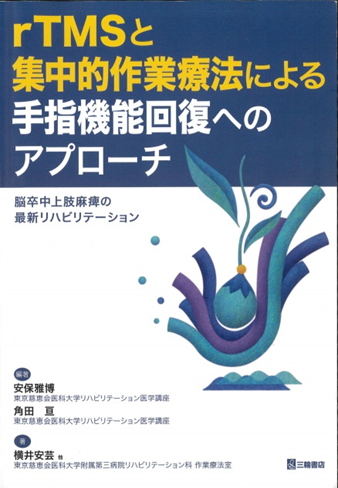 |
書籍名:rTMSと集中的作業療法による手指機能回復へのアプローチ |
| 著者名:安保雅博、角田亘(編著)・横井安芸(著) | |
| 出版社名:三輪書店 | |
| 発行年月:2010年07月 | |
| 脳卒中後遺症による上肢麻痺に対して、機能改善のために反復性磁気刺激と集中的作業療法を系統的に施行する手段を世界で初めて体系化した本です。症例報告もあり、少し専門的ですが、読み応えのある本です。(文責 安保雅博) |
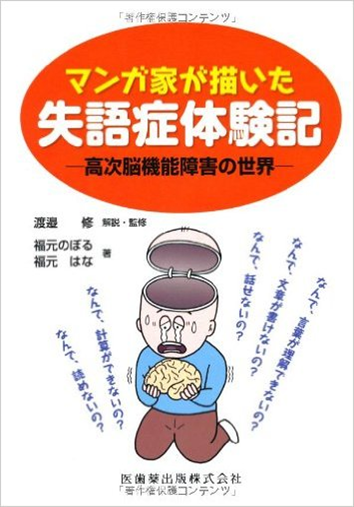 |
書籍名:マンガ家が描いた失語症体験記-高次脳機能障害の世界- |
| 著者名:渡邉 修(解説・監修) | |
| 出版社名:医歯薬出版 | |
| 発行年月:2010年05月 | |
| 左大脳半球に脳梗塞をわずらったマンガ家の方が、ご自分の実体験を、失語症ゆえに、言語で表現できない内容を、マンガを通して記述しました。奥様がその内容をサポートし、私が、医学的な解説を加えました。(文責:渡邉 修) |